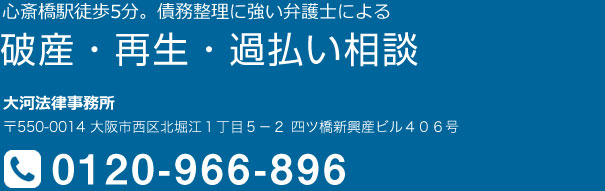一、はじめに
自己破産や個人再生の手続きの依頼をいただく中で、「身内に保証人になってもらっているのだけど・・・」といったご相談を受けることがよくあります。
そこで今回は、「主たる債務者が民事再生の手続きをした場合、保証人の責任はどうなるか?」という問題を取り上げます。
まず、簡単に事例を紹介します。
1.主債務者であるXは、個人再生の手続きを弁護士に依頼した結果、Xの1500万円の債務は5分の1の300万円に減縮されることとなりました。
2.Xの債務にはYという保証人が付いていました。
そこで、今回Xが個人再生手続きをしたことによって、保証人であるYにはどのような影響を受けることになるでしょうか。
二、再生計画の効力が及ぶ範囲について
この点、民法では、保証債務に「付従性(ふじゅうせい)」があることを規定しています(民法448条、457条等)。
「付従性」とは、簡単に言うと、主たる債務者に生じた事由は、原則として保証人にも効力を及ぼす、という性質のことです。そうすると、保証人であるYの債務もXと同じように5分の1の300万円に減縮されるとも考えられそうです。
しかし、民事再生法では、再生計画の効力が及ぶ範囲について
- 再生債務者
- すべての再生債権者
- 再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
と規定しています(民事再生法177条)。
ここでいう③は、保証人(今回のケースでいうY)のことを指しているわけではありません。
むしろ同条の第2項で、「……再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利……に影響を及ぼさない」と規定されており、保証人に再生計画の効力は及ばないということになります。
つまり、Xの手続きによっても、保証人Yの債務は5分の1の300万円に減縮されることなく、依然として1500万円のままということになります。
なお、破産手続きにおいても同様に、免責の効力が保証人には及びません(破産法253条2項)。
仮にXが破産した場合でも、Yは依然として1500万円の支払義務を負っているということになります。
三、まとめ
このように、主たる債務者が再生手続きにより負債を減縮されたとしても、保証人にはその影響がなく、依然として保証金額全額について支払義務が残ることとなります。
そして、このようなケースでは保証人は債権者から一括返済を求められることが通常ですので、保証人の方でも支払いの段取りや、場合によっては自己破産や個人再生といった手続きを検討していただく必要があります。
(2017年2月17日 執筆)
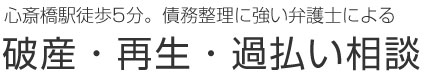
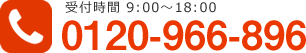
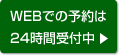


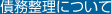





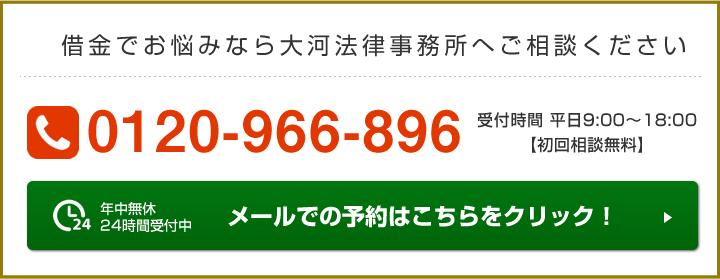

 大河法律事務所
大河法律事務所