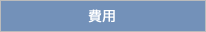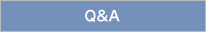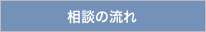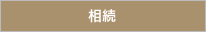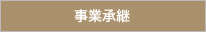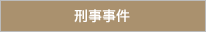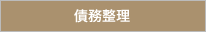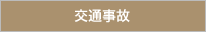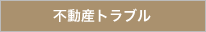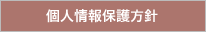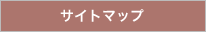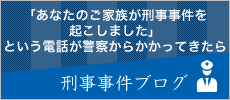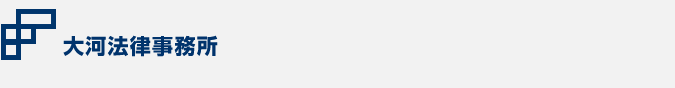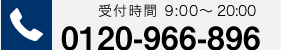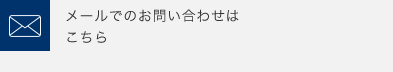相続
【目次】
相続手続きの全体像と知っておくべき留意点
(1)相続の大まかな流れ

ご覧の通り、中には期限のあるものもありますので、できるだけ早めの対応をする必要があります。
(2)相続が「争続」になる原因
相続人の一人が「自分が遺産を全て相続したい」と言ってきた場合や、被相続人が特定の人物に全ての遺産を相続させると言っていた場合に、取り分を巡って相続人間で激しい争いになるケースが非常に多いです。
これは、被相続人から受けた資金援助や被相続人の生前の介護の負担を原因として相続人の間で「不公平感」が生まれ、そういった感情の対立が相続というお金が絡む場面で一気に表面化するものと言えます。
(3)相続トラブルはお金持ちだけのものではありません
相続に関するトラブルは、「財産が5,000万円以下の家庭」で多く発生していると言われています。
相続財産が5,000万円を超える人は専門家に相談するなど、早くから対策を立てていることが多く、また、財産が多ければ、比較的分けやすいため問題が起きにくいといったことが考えられます。しかし、5,000万円以下の場合は、「うちにはたいした財産はないから」と言って、そういった対策がなされず野放しになっているケースがまま見受けられるのです。
ですが、「大した財産ではない」とはいっても、例えば家1軒で数百万円〜数千万円という価格になります。普段目にすることのない大金が動くときこそ、それぞれの取り分を巡って揉め事が起きやすいといえます。
法定相続人:相続人になる場合、ならない場合
相続を考えるうえでは、誰が相続人になって、誰が相続人にならないのかをまず確定する必要があります。
相続権がある人|法定相続人
基本的には、下記にあたる人が相続人になります。
亡くなった被相続人の配偶者(夫・妻)は必ず相続人になる
配偶者は常に相続人になります。
被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹も相続人になることができる
配偶者以外ではこれらの者も相続人となりますが、全員が同時に相続人となる訳ではありません。
というのも、民法では相続できる順位を1位から3位まで定めており、上位の相続人がいる場合、下位に当たる人が相続人となることはありません。
第1順位:被相続人の子供
なお、子供が既に死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫)が相続人となります(「代襲相続」と言います)。
第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
なお、父母も祖父母も存命である場合は、相続人により近い世代の父母が優先します。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
なお、兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子供が相続人となります(「代襲相続」と言います)。
非摘出子でも相続人になれる
嫡出子とは婚姻関係にある男女の間に生まれた子供のことをいい、非嫡出子は婚姻関係のない男女の間の子をいいます。非嫡出子の場合、父親が認知をしなければ父子関係が発生しませんので、その非嫡出子は相続人になることができません。
なお、以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、最高裁判所の判決を受けて民法の一部が改正され、平成25年9月5日以後に発生した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等と扱われることになりました。
養子も相続人になる
相続においては、養子も実子と全く同様に扱われます。また普通養子であれば、実父母と養父母の両方から相続することができます。
異母兄弟には相続権がある
相続を機に異母兄弟の存在が発覚する場合がありますが、例えば両親に離婚の経験があって、前婚の時に子どもがいた場合はその子どもも相続人になります。
胎児も相続人になる
不幸にも、お腹の中に赤ちゃんがいるような場合に夫が亡くなった場合であっても、相続の場面では(無事生まれることを条件に)お腹の赤ちゃんも相続人の一人として扱われることになります。
相続権がない人|相続欠格など
次に、相続人になれない人を確認しましょう。
内縁の夫(妻)は相続権がない
相続人になれる配偶者は、婚姻届を提出している正式な配偶者で、内縁の配偶者は基本的には相続人には含まれません。しかし、遺言書で内縁の配偶者に遺贈することによって財産を受け継がせることができます。
離婚した元配偶者
元配偶者との間に生まれた子供は相続人となりますが、元配偶者自身は相続人とはなりません。
再婚した配偶者の連れ子
配偶者はもちろん相続人となりますが、前夫の子は被相続人と養子縁組をしないと相続人にはなれません。
法に触れる行為をした者はなれない(相続欠格)
遺産相続において、相続人になるはずだった人でも、法に触れる行為をしたなどの事情があると、相続人になれません。
例えば・・・
- 故意に被相続人、相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させた者、死亡未遂などで刑に処せられた者
- 詐欺・脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げたり、遺言の取消・変更を妨げたりした者
- 被相続人が殺害されたことを知っていても告発しなかった場合
上記が該当項目になります。
遺言書の偽造を行った者は相続人になれない
被相続人の相続に関する遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者は、相続人としての地位を失うことになります。
法定相続分とは
自分が相続人にあたることがわかったとしても、具体的にどれだけの割合がもらえるのかといったことは知らない方が多いのではないでしょうか。
法定相続分|一般的な遺産相続の順位と割合
遺言書などがなく、特別な事情がない場合は下記のような順番及び割合で遺産相続が行われていきます。

相続で覚えておくべき3つの方法とその特徴
相続自体は、被相続人が亡くなると同時に自動的に発生します。ですが、その人の財産を相続するかしないかは、受け継ぐ側で決めるべき事柄でもあります。具体的な相続の仕方には次の3つの方法があります。
単純承認する場合:遺産の全てを相続する。
相続人が被相続人の権利義務を全て相続することを「相続の単純承認」といいます。つまり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
単純承認の方法
単純承認には特別な手続きは必要ありません。ただし、3カ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものと扱われます。
単純承認の注意点
プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全てを引き継ぐのが単純承認です。明らかにマイナス分が多い、あるいは多いかもしれない場合は「相続放棄」か「限定承認」を選ぶ必要が出てきます。
限定承認する場合:遺産の一部を相続する
限定承認とは、遺産相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナス分の財産を相殺し、財産が残ればそれを相続するという方法です。マイナス分が少なければプラスになりますし、マイナスの財産がプラスを超えていてもマイナスの部分を負担する必要はありません。ですので、プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれいくらあるかわからないといった場合に、とりあえず限定承認を選択するといったケースがあります。
限定承認の方法
限定承認は、単純承認の場合と違い一定の手続を行う必要があります。具体的には、「相続開始を知った時から3か月以内」に、相続財産の目録を作成の上、家庭裁判所に対して限定承認の申述を行います。
限定承認の注意点
限定承認は相続人全員が共同で行う必要があります。つまり、相続人の中に一人でも反対する人がいる場合には限定承認を行うことはできなくなりますので、注意が必要です。
相続放棄を行う場合:遺産の全てを放棄する
相続放棄とは、「私は相続財産を一切受け取りません」という宣言のことを言います。「被相続人にはプラスの財産は何もないけれど、マイナスの財産(借金)だけはある」といった場合に利用されるのが一般的です。他には、特定の相続人に財産を集中させたいような場合にも利用されることがあります。
相続放棄の方法
相続の開始があったことを知った日から 3カ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続人の範囲や法定相続分が変わってきます。
後から借金がわかった場合の相続放棄
被相続人が亡くなったときにはわからなかった借金の存在が、死後半年や1年以上経ってから判明する場合があります。相続放棄ができるのは、上で述べたように相続開始を知ってからの3カ月間が原則ですが、事情によってはこの3カ月間の開始時期を、借金の存在を知ったときからに延ばしてもらい、相続放棄が可能となる場合があります。自分が本当に親の借金を被らなければいけないのか、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
遺産を実際に分けるときの一般的な手順と流れ
相続を行う上で、どのような流れや手順で実際に財産が分けられていくのか(「遺産分割」と言います)、基本的な流れを確認しましょう。
相続開始から遺産分割までの流れ

遺言書によって分割する場合
被相続人が遺言書を残していた場合、遺言書に記載されている内容に沿ってそれぞれの遺産を相続人に分配する必要があります。基本的に相続人間で話し合う必要はなく、そのまま記載された内容でそれぞれの財産を引き継ぐことになります。
遺産分割協議で分割する場合
遺言書がない場合、誰がどの財産を受け継ぐのかを話し合って決めなければならず、この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。
まずは相続人の確定から
遺産分割協議を行うにあたり、最初にすべきことは相続人の確定です。被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本を入手し、相続人を確定させます。なお、この戸籍謄本等の入手は弁護士にて行うことが可能です(「職務上請求」と言います)。
遺産分割協議は、相続人全員で行われるものですので、後から相続人が出てくると遺産分割協議をやり直さなければなりません。そのため、最初にきっちりと相続人を確定することがとても重要です。
相続財産の調査を行う
次に相続財産の調査を行い、被相続人にどのような財産があるのかを確定させることになります。
話し合いによる遺産分割協議を開始する
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。ただし、相続人が遠方に散らばっている場合や、相続自体にあまり関心や利害関係がない相続人がいる場合には、書類の持ち回りで済ませてしまう場合もあります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で話し合った内容を文書にまとめ、「遺産分割協議書」として作成します。ここに相続人全員が署名・押印(実印が必要です)をすれば、各金融機関や証券会社等での名義変更手続きなどの相続手続きを進められるようになります。
遺産分割調停で分割する場合
次に、遺産分割調停によって分割する方法を確認しましょう。
話し合いができない場合に申し立てる
一部の相続人が協議に応じなかった場合や、遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合には、遺産分割の調停という手続きを家庭裁判所にて行うことになります。
遺産分割調停で話すこと
遺産分割調停では、一般的に以下の事項について段階的に内容を確定していくことになります。
- 相続人の法定相続分の範囲の確定・確認
- 遺産の範囲・評価の確定
- 特別受益・寄与分の有無・評価の確定
- 具体的相続分の確定
- 遺産分割方法の確定
遺産分割調停が不成立になった場合、自動的に審判に移行する
調停もあくまで話し合いの手続きですから、ここでも話がつかなかった場合には遺産分割審判に移行され、最終的には裁判官が判断を下すことになります。なお、別の手続きではありますが、自動で移行し別途審判の申立てをする必要はありませんので、そのまま調停委員の指示に従ってください。
分け方が決まったあとの手続きは誰がするのか?
相続の手続きには、見たこともない書類を複数用意しなければならず、しかも一つでも足りない書類があると、手続きを完了することができません。そのような手続きをご自身ですべて行おうとすると、かなりの時間と労力を必要とするのが実情です。
そこで
【遺産相続手続き代行業務のご案内】
専門家にすべてお任せにしてしまい、楽になりませんか。日常の貴重な時間をぜひ取り戻してください。
遺産相続時に遺言書があった場合
遺言書がある場合、その記載内容に沿って遺産分割を行うことになります。ここでは遺言書の効果と残しておくべきメリットをご紹介します。
遺言書とは?
遺言書とは、被相続人が自ら財産の分け方を指定するもので、相続人同士で分け方を巡って争いが起きないようにするための、最も有効な手段と言えます。
遺言書を残しておくメリット
相続人同士のトラブルを予防する効果が期待できるだけでなく、特定の相続人に遺産を集中させたい場合や、相続人でない者にも遺産を渡したい場合でも、遺言書を作成しておくことで遺産相続をさせることができます。
遺言書の種類
遺言書の作成にはルールがあり、そのルールに従っていない遺言書には効力が認められません。そして遺言書には「普通方式の遺言書」と、「特別方式の遺言書」の2種類の形式がありますが、ここでは普通方式の遺言書、その中でも特に利用されることが多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を取り上げます。
自筆証書遺言
・被相続人が書面に
・遺言書の全文、作成年月日、遺言者の氏名を
・自筆(パソコンは不可)で記入し
・自身の印鑑を押印する
という方式で作成されます。民法で定められている遺言の方式としては一番簡単なものとお考えください。
公正証書遺言
・法に定められた手続きに従い
・公証人(公証役場におられます)に対して遺言内容を伝え
・公証人がこれを遺言書に落としこむ形で作成し、これを保管する
という方式です。上記の手順を踏んで作成するため、完成には時間がかかりますが、公証人との面談の上作成されることから、その信憑性が問題となりにくく、遺言書の効力に後日疑義が生じにくいというメリットがあります。
必ず遺言執行者を指定しておく
遺言書が効力を発揮するのは遺言者が死亡してからになりますので、遺言の内容が間違いなく実行されるために、「遺言執行者」を決めておくのがポイントです。指名していなくても、家庭裁判所が決めてくれることになっていますが、あらかじめ自分で決めておけば処理が簡単になります。
遺言書を見つけたら家庭裁判所に持っていく
遺言書の内容は被相続人の最終意思でもあるので、その内容が後日他人によって歪められないようにするのが大切です。家庭裁判所は検認というものを行っており、遺言書の偽造、変造を防ぐことをしています。もし、遺言書に違和感を覚える場合は、家庭裁判所で検認を受けていただき、遺言書の効力を再確認されることをお勧めします。
遺留分の侵害を受けた場合
遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟や姉妹以外の相続人に対して最低限の遺産相続分を保証する相続割合のことを言います。被相続人の遺言などにより相続人の相続財産が全く残らないことを避けるために設けられた権利で、子の代襲相続人にも遺留分を請求する権利が認められています。遺留分を請求できる人を遺留分権利者と言い、遺留分の請求をする事を、遺留分減殺請求と呼びます。
遺留分の計算方法
遺留分を計算する際は、通常の法定相続分とは違った分け方をし、手順としては以下のようになります。
1:生前贈与した財産を加えて計算する
2:不当に売却した財産を加算
3:被相続人の借金は控除する
4:遺留分の基礎となる財産の算定
こういった金額の加算や減算をやり直し、遺留分を算定する基礎財産を算出します。この財産に上記の遺留分割合をかけた分が、各相続人が遺留分として最低限相続財産に対して有している持分となり、式としては以下の通りです。
【遺産の金額×遺留分の割合=遺留分の金額】
取り戻すには遺留分減殺請求
遺留分減殺請求は、最低限度の相続財産を得る権利が法律によって与えられている行為のことで、主に以下の3つの方法があります。
1:内容証明郵便で請求する
2:遺留分減殺請求調停で請求する
3:遺留分減殺請求訴訟を起こす
遺留分は放棄することもできる
遺留分を放棄するケースとしては、他の相続人が遺留分を放棄させて、長男にすべての財産を相続させるというような場合に行われます。他にも遺留分がいらないというケースも考えられますが、どちらにしても裁判所に遺留分放棄の申し立てを行い、許可をもらう必要があります。
取り扱い分野
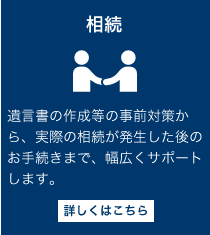 |
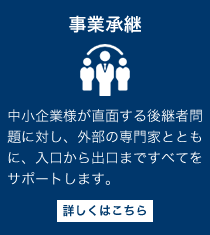 |
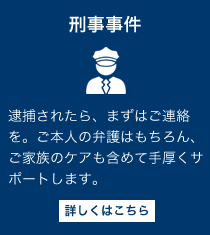 |
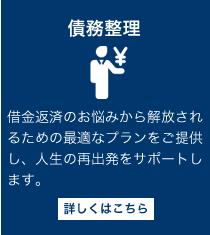 |
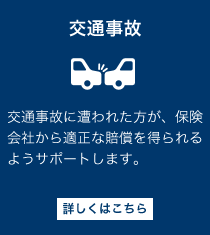 |
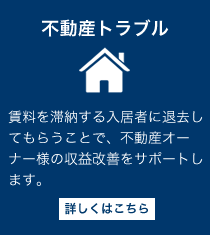 |

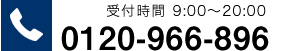

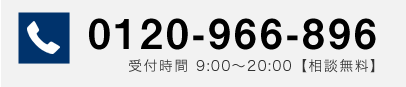
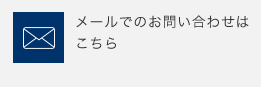

 大河法律事務所
大河法律事務所